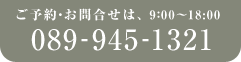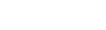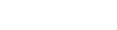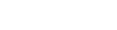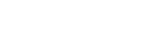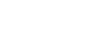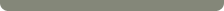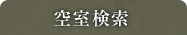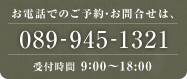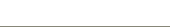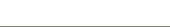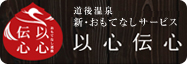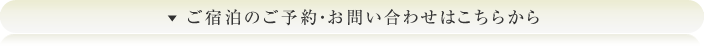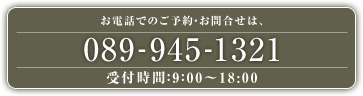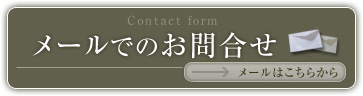マイントピア別子ウインター・イルミネーション

マイントピア別子ウインター・イルミネーション
開催期間 2019年12月1日~2020年2月29日
開催場所 マイントピア別子
マイントピア別子端出場記念館入口周辺に約12万球の電飾によるイルミネーションを点灯。端出場記念館4階の別子温泉~天空の湯~のご利用もオススメ。
もうすぐクリスマス
もうすぐクリスマス✨
ロビーのクリスマス装飾も 完成しました❗(^^)
サンタの帽子やトナカイ、 小さいお子さま用のサンタコスも ご用意してます(*^^*)
ぜひフレームに入って 皆様で思い出の1枚を…

早めの忘年会!!!
こんにちは!!!料理長の藤田です。
今回のブログは、私達調理場の忘年会をあげさしていただきます。
ホテル業は、年末忙しくなるので毎年早めに開いています。普段なかなか話せないスタッフ、コミュニケーションが取れてい
ないスタッフもお酒を交わして和気藹々と楽しんでる光景を見ると責任者として嬉しく思い、更にこのメンバーと前向きに仕
事ができる様にも捉えることもでき、私の活力の一部になりますね!!!
コミュニケーション不足の時代ともいわれ問題になっていますが、今の責任者の役目の1つとして若い世代に、得意 不得意
関係なく、そういった経験 成長する場を用意し、あとは各自で参加するかしないかですね。
少なくとも私は、成長できたと思いますし今でも誘って頂いた先輩方には、感謝しています。
今後更に結束を深め、茶玻璃のホテルが飛躍できるよう頑張っていきたいと思います!!!
皆様、気温が急激に下がっていますのでお身体には、充分気をつけてくださいね。
以上 藤田でした!!!
中山池自然公園イルミネーション

中山池自然公園イルミネーション
開催期間 2019年12月1日~2020年1月3日(予定)
開催場所 中山池自然公園
今年も中山池自然公園の一部を利用した、これまでより縮小したイルミネーションになるが、都会の華やかな電飾とは異なる自然公園内の木々を電球で彩る。
広田じねんじょまつり

広田じねんじょまつり
開催期間 2019年12月1日
開催場所 道の駅ひろた「峡の館」
砥部町の特産品「自然薯」の販売や、自然薯の目方当てクイズ、「とろろかけそば」「麦とろごはん」等、自然薯料理の販売も行われる。